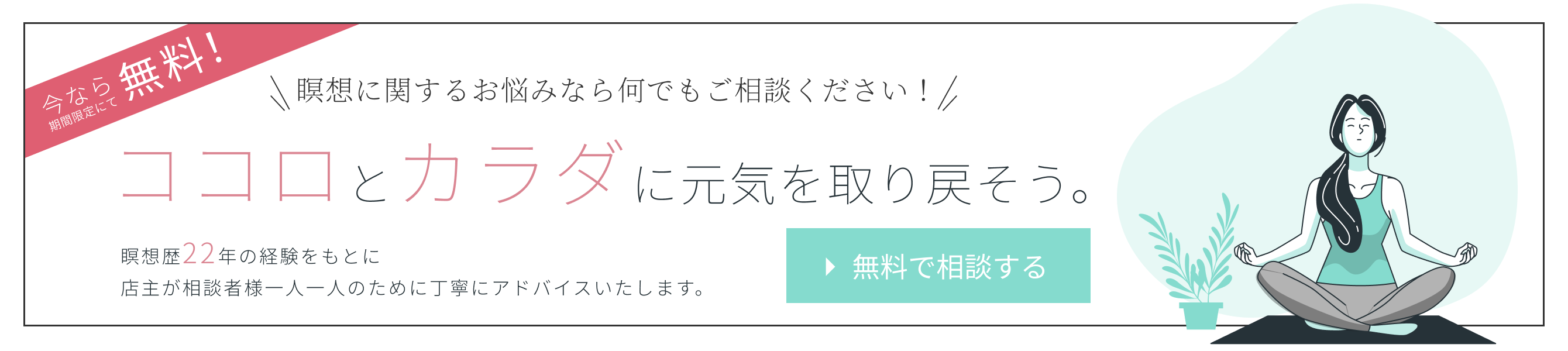◎タントラにおける曼荼羅(マンダラ)
タントラ Tantraとは、元々「織機」や「織物」あるいは織り物の「縦糸」を意味するサンスクリット語で、ヒンドゥー教や仏教において、様々な思想が織りなされて体系化されていった教義を表しています。
ここでは、仏教タントリズムにおける経典の成立過程に則した「タントラ」の分類と、それぞれのタントラにおける代表的な曼荼羅やマンダラの位置づけについて概略をまとめました。
◎タントラの分類
14世紀のチベットの仏教学者プトゥンが確立した分類によると、タントラは成立過程の順序に応じて次の4つに分けられます。
【1】作タントラ(クリヤー・タントラ Kriya Tantra)・・・・・・・・・・・・・前期密教[2~6世紀]
【2】行タントラ(チャリヤー・タントラ Charya Tantra)・・・・・・・・・・・中期密教[7世紀前半]
【3】ヨーガ・タントラ (Yoga Tantra)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中期密教[7世紀後半]
【4】無上ヨーガ・タントラ(アヌッタラ・タントラ Anuttarayoga Tantra)・・・後期密教[8~11世紀]
この四分法では、各々のタントラに含まれる密教経典、陀羅尼、儀軌、観想法などによって分類されています。
では、それぞれの内容について見ていきましょう。
【1】作タントラ
『蘇悉地経』『蘇婆呼童子経』『不空羂索神変真言経典』などの経典が、この「作タントラ」のタントラ・グループに当てはまります。
作タントラの「作」とは、作法、方法を意味し、「作タントラ」は呪文、陀羅尼(だらに/ダーラニー)、諸仏の供養の仕方、壇のつくり方、手印の結び方など、儀礼の作法を主要な内容としているところが特徴です。
こうした儀礼主義は、ブラーフマニズム(バラモン中心主義)において重視されるもので、当初、仏教では儀礼主義に対して批判的であったものの、大乗仏教の興隆によって、こうしたバラモン僧たちの儀礼が仏教の僧たちに取り入れられていきました。
ただし、儀礼行為が悟りをもたらすと考えられていたのではなく、あくまでもこうした作法は補助的なものと考えられていたと思われます。
また、この頃の大乗仏教徒たちは、仏に水・香・花などを捧げる供養(プージャー)するようにもなっていました。
シンプルな構図のマンダラも、この頃から供養に用いられていたようで、19世紀末に編纂されたチベットにおけるマンダラ理論の集大成である「タントラ部集成」に収載されている139点中のマンダラのうち第19までが「作タントラ」に属すると考えられています。
【2】行タントラ
7世紀に成立したと考えられる『大日経』が「行タントラ」の主要経典です。この経典によって仏教タントリズム(密教)が確立されたとされます。
この『大日経』の中心課題は悟りです。この経典では、外的・身体的行為である儀礼を重要視しつつも、儀礼の内化あるいは精神化が進みました。
曼荼羅をつくり、それにもとづいて入門儀礼を行ない、そしてヨーガによる瞑想を行うようになったのです。
ヨーガによる瞑想とは、精神を集中し、神や仏といった「聖なるもの」をあたかも眼前に存在するかのように生み出して観るというもので、こうした瞑想は続く「ヨーガ・タントラ」「無上ヨーガ・タントラ」においてさらに発展して「観想法(サーダナ)」が実践されていきます。
古典ヨーガでは、心のはたらきを制御して「俗なるもの」を消して「聖なるもの」の顕現を目指すものでしたが、むしろ心のはたらきを利用して「俗なるもの」を強めて聖化することで「俗なるもの」と「聖なるもの」とを一体化しようとしたのがタントリズムと言えます。
「行タントラ」に含まれるマンダラのひとつが『大日経』に基づく「大悲胎蔵生マンダラ」(胎生マンダラ)ですが、インドで成立したほとんどのマンダラを受け入れたと思われるチベットにおいても、ほんのわずかな点数が残されているだけで、このマンダラは後世にはあまり勢力をもたなかったと考えられます。
また、『タントラ部集成』では二十番の「現等覚大日一二二尊マンダラ」が「行タントラ」のグループに当たります。
胎蔵(界)曼荼羅や金剛界九会曼荼羅は、いずれも日本に伝えられ、今日も残っている曼荼羅の中でも最古のもので、仏教タントリズムが確立した時期のマンダラの特徴を呈しています。
胎蔵(界)曼荼羅は、基本的に『大日経』に基づきながらも、他の経典の記述を取り入れ、様々な変化や修整を経て現在の形にまとめられたものと考えられますが、この胎蔵(界)曼荼羅がどのようにして成立したかは明らかではありません。
空海が唐から日本に持ち帰った両界曼荼羅を受け継いで転写された現図曼荼羅や、チベットに伝えられた『大日経』のマンダラには、ヒンドゥー教の神々が描かれいます。このことは「行タントラ」の系統の仏教はヒンドゥー教から大きな影響を受けていることを示しています。続く「ヨーガ・タントラ」においてはこうしたヒンドゥー教色は弱まっていきます。
【3】ヨーガ・タントラ
「ヨーガ・タントラ」に対応する代表的な経典は『金剛頂経』で、この経典に基づくマンダラが金剛界曼荼羅です。
「ヨーガ・タントラ」の実践にあたって、行者たちは観想法によって仏を眼前に出現させ、その仏を供養するのにとどまらず、さらに仏と“一体となる”ことを目指しました。
例えば、金剛界曼荼羅を用いた観想法では、マンダラが映し出す“世界”あるいはマンダラに現れる“仏”と行者が“一体である”ことを感得するのです。
これより前の「作タントラ」や「行タントラ」の実践にあっては、眼前に出現する仏と自分たちとは別の存在であり、仏のまえにいる行者自身を意識していたという点で、この「ヨーガ・タントラ」においてマンダラの世界と一体となる観想法がさらに深化し発展したと言えるでしょう。
曼荼羅の構造を見ても、金剛界曼荼羅と胎蔵曼荼羅とは根本的に異なります。
胎蔵曼荼羅までは、上部が東を意味し、本尊は西を向いていましたが、金剛界曼荼羅では下部が東を意味し、本尊は東を向いています。
また、従来のマンダラが仏部・蓮花部・金剛部の三部によって構成されていたのに対し、金剛界曼荼羅では如来部・金剛部・宝部・法部・羯磨部という五部によって構成されています。
これらの五部は中央と四方に配置され、金剛界曼荼羅の核を形成しています。それぞれに対応する位置とシンボルは以下の通りです。
中央:如来部・・・大日如来
東方:金剛部・・・阿閃如来:金剛
南方:宝部・・・・宝生如来:宝珠
西方:法部・・・・阿弥陀如来:蓮花
北方:羯磨部・・・不空成就如来:二重金剛(羯磨)
【4】無上ヨーガ・タントラ
一般に後期密教と言われる「無上瑜伽タントラ(無上ヨーガタントラ)」では、高度のヨーガの技術を用いながら、「ヨーガ・タントラ」で獲得された実践法をさらに押し進めていくことになります。
「無上ヨーガ・タントラ」の実践法には、これまで仏教とはあまり関連の無かった血・骨・皮の儀礼といった、土着文化(シャーマニズム)の要素も積極的に取り入られるようになりました。
また、性に対する考え方も大きく変化しました。従来の仏教では、抑圧すべきもの、切り捨てるべきとされてきた「性」を、「俗なるもの」ではなく肯定すべき「聖なるもの」というする考え方も現れ、性行為が悟りを得るための手段として用いられるようにもなりました。
仏の姿もこれまでとは異なる姿で描かれるようになり、無数の腕があり、血に満たされた頭蓋骨杯を持ち、妃を抱くといったような異形の姿の仏も登場しました。
さらにこの「無上ヨーガ・タントラ」のグループは、対応する経典がそれぞれ『秘密集会タントラ』『ヴァジュラバイラヴァ・タントラ』などの父タントラ、『チャクラサンヴァラ・タントラ(勝楽タントラ)』などの母タントラ、『呼金剛タントラ』や『時輪タントラ』などの不二タントラとして、三つに細分されます。
日本においては、『呼金剛タントラ』など、いくつかの「無上ヨーガ・タントラ」の漢訳経典が伝えられたものの、実践としてはほとんど行われなかったようです。
「無上ヨーガ・タントラ」の系統に当たる経典は、8〜9世紀以降、インドにおいて編纂され、それらに基づいた実践も行われましたが、「無上ヨーガ・タントラ」の実践はとりわけチベットにおいて盛んに行われました。
『タントラ部集成』では半数以上のマンダラが「無上ヨーガ・タントラ」に基づくものです。
『チャクラサンヴァラ・タントラ(勝楽タントラ)』の伝統は、今日のネワール密教においても残されているようですが、印可を受けた者以外はこれに接することはできません。
以上のように、仏教タントリズムにおける経典の変遷とそれに伴うタントラの実践方法の発展にともない、マンダラの中に表される仏や世界も大きな変化を遂げ、さらにはマンダラの観想法も進化・深化していったことがうかがえます。
参考:「マンダラ観想と密教思想」(立川武蔵 著/春秋社)